根抵当権とは?特徴と普通抵当権との違い

お金について勉強中
『根抵当権』について教えてください。
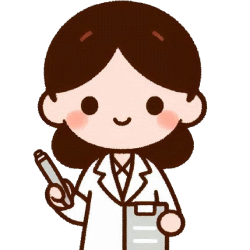
カードローン研究家
『根抵当権』は、一定の範囲に属する特定されていない債権を極度額の範囲内で担保する抵当権です。極度額とは、融資限度のことです。

お金について勉強中
通常の抵当権との違いは何ですか?
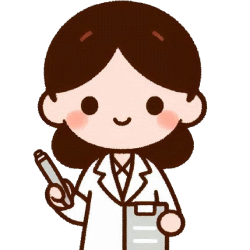
カードローン研究家
通常の抵当権は特定の債権のみを担保する一方、『根抵当権』は一定の範囲に属するすべての債権を担保します。また、『根抵当権』は物件の所有権を移転しない点でも通常抵当権と異なります。
根抵当権とは。
カードローン用語の「根抵当権」とは、あらかじめ決められた額の範囲内にある、特定されていない債権を担保にする抵当権のことです。これに対して、通常の抵当権(普通抵当権)は、特定の債務を担保するものです。
根抵当権とは

-根抵当権とは-
根抵当権とは、不動産の将来取得見込みを担保とし、その不動産を取得した場合に自動的に抵当権が発生する制度です。借入の際に担保として不動産の取得を約したときに設定されます。つまり、まだ不動産は取得していないものの、将来取得したときに自動的に抵当権が設定されるため、担保として利用できるのです。この点が、不動産をすでに所有している場合に設定する「普通抵当権」とは異なります。
根抵当権の特徴

根抵当権の特徴として挙げられるのは、まず目的物を特定しない、いわゆる「総括的」な抵当権であることです。これにより、将来取得するすべての同種の財産を担保に取ることが可能になります。そのため、動産を担保にする場合には極めて有効な手段となります。次に、根抵当権は設定の際に公示する必要がありません。つまり、第三者に公開せずに設定することができるため、秘密裏に担保を設定したい場合に適しています。ただし、この非公示性は第三者にとって不利にもなり得るため、注意が必要です。
普通抵当権との違い

普通抵当権との違いは、担保物件の範囲にあります。普通抵当権では、担保物件の特定が必須ですが、根抵当権では担保物件として登録免許税を納付した範囲内のすべての不動産が対象となります。つまり、根抵当権では、担保物件を特定する手間が省かれ、かつ、将来取得する不動産も担保に組み込むことができます。また、担保不動産が滅失した場合でも、根抵当権は消滅せず、代償金が担保に充てられます。
根抵当権の設定と実行

根抵当権の設定と実行
根抵当権を設定するには、借入者と金融機関が抵当権設定契約を締結する必要があります。契約には、対象となる不動産、抵当権の順位、融資金額、返済期限などが記載されます。契約書と抵当権設定登記を完了することで、根抵当権が成立します。
根抵当権の実行は、借入者が債務を履行しない場合に行われます。金融機関は債務不履行を通知し、一定期間内に返済されなければ、裁判所に競売申立てを行います。競売によって不動産が処分され、得られた代金から債務が清算されます。
根抵当権のメリットとデメリット

–根抵当権のメリットとデメリット–
根抵当権には、メリットもデメリットもあります。まず、メリットとして、対象となる不動産以外の財産も担保として利用できる点が挙げられます。住宅ローンなどで利用されることが多い普通抵当権では、不動産だけが担保になりますが、根抵当権では動産や有価証券などを担保として設定できます。そのため、担保価値の範囲が広くなり、資金調達が容易になるという利点があります。
一方で、デメリットとしては、設定や登記の費用が普通抵当権よりも高くなる可能性があります。根抵当権は、普通抵当権よりも手続きが複雑になるため、手数料や登録免許税などが割高になります。また、担保財産を自由に処分できないという制約もあります。根抵当権が設定されている不動産や動産を処分する場合は、債権者の同意が必要となり、処分に制限が生じます。
